「言葉で人生を変える」と聞くと、少し大げさに思えるかもしれません。
でも、ひすいこたろうさんの言葉に触れた人たちは、「気づいたら心が軽くなった」「明日が楽しみになった」と口をそろえます。
そんな彼は、顔を出さず、どこかミステリアスな存在。
本名や年齢、大学などの詳細もあまり知られていませんが、
その謎めいた雰囲気こそが、多くのファンを惹きつけてやまない理由のひとつです。
この記事では、ひすいこたろうさんの“素顔”を探るように、
顔出しの有無や理由、年齢・学歴・経歴などを改めてまとめてました。
読めばきっと、彼の「言葉の力」がどこから生まれているのか、そのヒントが見えてくるはずです。

ことばがやさしく救われます
ひすいこたろうって何者?
「え、ひすいこたろうって誰?」という方も多いでしょう。
私自身、最初は名前だけをどこかで聞いたことがあって、「なんとなく自己啓発系?」くらいの印象でした。
でも調べてみると、「言葉で心を揺さぶる表現者」という輪郭が浮かび上がってきて、その存在感にちょっとワクワクしました。
ここでは、肩書き・活動スタイル・特徴を軸に、なるべくクリアに彼のイメージを伝えたいと思います。
肩書き・活動ジャンル、発信スタイル
ひすいこたろうさんは、複合的な肩書きをもちながら活動している“言葉の表現者”です。
主に見られる肩書きは以下のとおり:
- 著述家/作家
多数の書籍を発表しており、特に人生観・言葉・自己肯定感・物語性をテーマにしたものが目立ちます。
- 自己啓発発信者
言葉を用いて、日常や心・あり方に働きかけるメッセージを届ける活動が中心。ブログ・SNS・動画で「名言セラピー」という切り口で発信しています。
- コピーライター/言葉のデザイナー
言葉を「ただ伝える」だけでなく、「響かせる」ための工夫を重ねる表現者として、自称・評価されている側面もあります。
- 心理カウンセラー的な要素
心理学を学んだという記載や、心の在り方に触れる表現が多いため、心理支援や相談寄りの要素も感じられます。
これらを総合すると、「著作+発信メディアを通じて“言葉”を武器に、心や意識に働きかける人」と言えそうです。
彼の発信スタイルは意外とシンプルで、それでいて深みがあります。
重厚すぎず、優しさと問いかけを含む語りが“聴き手/読み手”と近い距離感をつくります。
主なプラットフォーム:
- YouTube「名言セラピー」チャンネル
「1分でハッピーになれる名言セラピー」というテーマで、短いメッセージ動画を定期配信しています。
- ブログ/Amebaオフィシャルブログ
日々の思いや言葉を文章で表現・更新しており、ファンとのストック型コミュニケーションとして機能しています。
- SNS(Instagram 等)
ビジュアルと言葉を掛け合わせた投稿が多く、フォロワーとの交流も活発です。
- 出版物
書籍という形で言葉を残すことにも力を入れており、「3秒でハッピーになる名言セラピー」など代表作があります。
このように、動画・文章・書籍を横断しながら「名言・メッセージ」を届けるマルチチャネルスタイルが彼の武器と言えそうですね。
代表作・テーマ性・魅力のポイント
言葉で「気づき」を促す作品が多いのが彼の特徴です。
代表作としてよく挙がるタイトルを通して、そのテーマ性・魅力を見てみましょう。
代表作例:
- 『3秒でハッピーになる名言セラピー』
- 『今日、地球人をやめる。』ほか、人生・存在・物語を扱う書籍群
これらから感じられるテーマ性や強みを挙げると:
- 短い言葉で深く響かせる
長い評論・解説よりも、一言・ワンメッセージで心に残るような言葉選びを意識しているようです。
- 日常を“物語化”する視点
普通の風景や出来事に物語性を感じさせる見方を促す表現がよく見られます。
- 読者との対話性・余白を残す
教え切るのではなく、問いを残し、自分で考える余地を持たせる語り口。
- 言葉のフィルター・編集者としての視点
他者の言葉や思想を “自分のフィルター” で料理して提示する構成力が魅力です。
私自身思うのは、ひすいこたろうさんは「言葉の案内人」なんじゃないか、ということです。
ただ“メッセージを伝える人”ではなく、読む人自身が言葉の中を旅する手助けをする人。
言葉を媒介に、こちら(読者)の内側を照らすような役割を果たしているなと感じます。
ひすいこたろうの顔写真ある?顔出ししない理由は?
「この人、顔見えるのかな?」――
ファンやはじめて彼の名前を知る人が最初に抱く疑問の一つかもしれません。
ネットを探してみたところ、はっきりとした顔写真や公的な素顔の写真はほとんど見つからないというのが実態のようです。
ここでは、“顔写真の有無”と“なぜ顔出しをしないのか”という理由にまつわる情報を、
できるだけわかりやすく整理してお伝えします。
顔写真はある?それとも「非公開」?
まず、確認できることから。
- 公式ブログやプロフィール欄などには、顔をはっきり映した写真は掲載されていません。
- YouTube「名言セラピー」の動画でも、本人が真正面から顔を明らかに映している映像は、目に付くものは少ないようです。
- その一方、「顔出しNG作家」として紹介されたブログ記事などもあり、本人が意図的に顔を伏せるスタイルをとっているとの見方が強く語られています。
- また、ファンの体験記によれば、あるイベントで撮影に応じてくれた(=顔を見せてくれた)という記述もあります。
たとえば、フランスで会ったファンは「写真撮影に応じてくださった」と書いています。
このように、「完全に顔ゼロ」とは言い切れないものの、
公に顔を全面に出すことは避けている印象が強いのです。
講演会に参加された方がこたろうさんの印象をブログで記されていたので、紹介させていただきますね。
実際のこたろうさんは、優しい目をした、ファンキーな服装の紳士でした。
普段は、浪人生みたいな服装をされているらしいのですが。
アメーバブログ
顔出ししない理由として語られているもの
では、なぜ彼は顔出しを控えるのか?公表されている情報とファン・関係者の証言をもとに、“有力な説”をいくつか紹介します。
1.プライバシー保護・家族を守るため
これが最もよく語られている理由です。
顔が知られることで、家族やプライベートな関係性に負担がかかることを避けたい、という考え方が背景にあるようです。
あるまとめサイトでは「家庭で話し合った結果、家族を守るために顔出ししないと決めた」との説明も見られます。
2.言葉・メッセージを際立たせたいから
顔を見せると、どうしても外見や雰囲気で印象が先に来てしまうことがあります。
彼は「見た目ではなく、言葉そのもの」に注目してもらいたいスタンスをとっている、との声も少なくありません。
顔を出さないことで、言葉の響きや内容そのものが先に届くようにしている可能性があります。
3.妻からの言葉
インタビューや対談で、「嫁に“私の旦那とわからないように”と言われている」という話が出たことがあるとの情報もあります。
ただ、これは本心かジョークかわからない部分もあるため、あくまで“語られている話”として扱ったほうが安全です。
4.場・イベント設計や演出のため
撮影制限を設けたり、会場で顔を見えにくく調整したりする “場の演出” という可能性も挙げられます。
たとえば、あるイベント参加者は「会場で顔が映らないような配慮がされていた」と書いています。
“顔出ししない”スタイルの強みと課題
このようなスタンスには、実は面白い効果も、注意点もあります。
強み・メリット
- 言葉に集中してもらえる
顔や見た目ではなく、「言葉そのもの」「メッセージ」が先に心に届きやすくなる可能性があります。
- ミステリアスさ・興味を引く要素
素顔を知ることができないというミステリアスさが、ファンの興味を引きつける側面があります。
- プライバシー保護・トラブル軽減
顔を公開しないことで、悪意ある中傷・プライバシー侵害のリスクを抑えられるという面もあるでしょう。
注意点・リスク
- 信頼感・親近感の損失
顔が見えないことで、「本当に実在するのか?」という疑念や距離を感じる人もいるかもしれません。
- 露出・宣伝面で制限が出やすい
顔を使ったプロモーション(表紙・ポスター・テレビ出演など)で不利になる可能性もあります。
- ファンとの距離感・扱い方の難しさ
親近感を保ちつつ謎を残す演出のバランスが問われます。
ひすいこたろうの年齢や本名、大学、経歴など調べてみた!
ひすいこたろうさん――ミステリアスな雰囲気をまといつつ、言葉で多くの人の心を揺さぶる発信者。
だからこそ、「この人、何歳なんだろう?」「本名や学歴は?」という素朴な疑問が湧いてくると思います。
ここでは、ネット上での情報をベースに、プロフィールの“輪郭”を浮かび上がらせてみます。
ただし、確証を得にくい点も多いため、「言われている」「可能性として」といった表現を交えてお伝えします。
年齢・生まれ年について
公的な生年月日の明示はなく、「1980年代・1990年代生まれ」などといったあいまいなプロフィールも見当たりません。
その代わり、いくつかの情報ソースで以下のような記述があります。
- あるプロフィールサイトでは、「弟が1973年5月生まれで50歳(2023年時点)」という情報をもとに、ひすいこたろうさんも 51歳以上 とされている。
- 他のサイトでは「誕生日は8月13日」「年齢は51歳以上」という記載も見られます。
弟さんは、株式会社和僑商店ホールディングス代表取締役をされている実業家の「葉葺正幸さん」(はぶきまさゆき)という方とだいわれています。
それが本当なら、苗字は『葉葺』さんになりそうですね。
年齢に関しては、現在50代中盤~後半あたりではないか、という推測が立ちます。
ですが、あくまで“外部情報をつなぎ合わせた推定”と捉えるのが安全です。
本名・改名の話
「ひすいこたろう」という名前はおそらくペンネーム・芸名であり、本名は公表されていないようです。
ただし、ネット上には以下のような説も流れています。
- 「葉葺(はぶき)正幸」という名前が本名ではないか、という表記を扱うサイトがあります。
- ただし、著者本人や公信機関がこの名前を認めているという確かな証拠は見つかっていません。
- また、過去に彼自身のブログで「ひすいこうたろうを辞めます。実はすでに改名しました。新しい名前は“マグネシウムこたろう”」というエントリーがありました。
- とはいえ、この改名宣言がジョーク寄りなのか、本気なのかは明言されておらず、ファンの間では「話題性・表現」として受け止められている節もあります。
したがって、本名と改名情報は「憶測の域を出ない」扱いが適切でしょう。

学歴・大学について
学歴・大学卒業についても、信頼性の高い情報は少ないですが、いくつかヒントとなる記述が見られます。
- 公式の自己紹介・過去ブログ投稿で、「学歴社会だった時代」「大学進学経験」への言及があることが確認できます。
- しかし、「どの大学に入ったか」「卒業したかどうか」という明示は見つかりませんでした。
- 内容から読み取れるのは、「勉強・学びに関する葛藤」や「社会・時代背景における学歴重視への反省」などを語る文章が複数存在する、という点です。
このあたりから強く言えるのは、「学歴がすべてではない」「学び続けることの意味を重視する姿勢」が、彼の言葉・表現の根底にあるテーマのひとつであるということです。
経歴・キャリアの軸(実績・活動から見る)
学歴よりもはっきり見えるのが、ひすいさんの“活動の足跡”です。
こちらは比較的確かな情報が複数記録されていますので、信頼度も少し高めに見てよいでしょう。
心理学・学びのスタート
- 公的プロフィールでは、「衛藤信之氏から心理学を学んだ」「心理カウンセラー資格を取得した」と記載されています。
- この心理的・内面に向かう学びは、後の著作・発信スタイルに大きな影響を与えたと想像できます。

出版・著作活動・受賞
- 2005年、著書『3秒でハッピーになる名言セラピー』が出版され、ディスカヴァーMESSAGE BOOK大賞 特別賞を受賞しました。
- 以降も『あした死ぬかもよ?』『今日、誰のために生きる?』など、多くの著作を世に出しています。
- また、著作だけでなく、セミナー・講演会・オンライン配信(YouTube「名言セラピー」など)でも活発に活動しています。
このように、著作発信+対面/オンラインでの講演・セミナーが彼の主要なキャリア軸と言えるでしょう。
見るべき視点・発信スタイル
ひすいさんのプロフィール説明において印象的なのは、「作家・幸せの翻訳家・天才コピーライター」という肩書きが併記されていることです。
「翻訳家」は比喩的意味が大きいようで、「人の心・思いを“他者に届く言葉”に翻訳する人」というニュアンスで使われているようです。
また、モットーとして「視点が変われば人生が変わる」が掲げられており、ものの見方の変化を通じて心・人生を変えていくことをテーマにしていることがはっきり記されています。
まとめると、、
ここまでを踏まえて、私なりに「ひすいこうたろうさんはこういう人だ」という像を描いてみます。
ただし、「断定」は避けたいので“仮説・可能性を含む輪郭”として受け取ってもらえたら嬉しいです。
- 年齢はおそらく 50代中盤~後半 あたりだと推測される
- 本名は公開されておらず、「葉葺正幸」説など複数の憶測があるが、確証なし
- 学歴・大学の情報は不明だが、学びや教育への言及が多く、学び続ける姿勢を重視している
- 経歴としては、心理学学習 → カウンセラー資格取得 → 出版・著作活動 → セミナー・講演・発信活動へと軸を広げてきた
- その過程で、“言葉で人の心に響かせる表現者”として独自の立ち位置を確立している
このように、謎のベールがかかっていながらも、「学びと表現を重ねた発信者」「言葉の翻訳者として、“視点を変える”ことを大事にする人」という印象を持ちます。
最後に
顔を出さず、個人情報もほとんど明かさない――
それでもなお、多くの人がひすいこうたろうさんの言葉に惹かれるのは、
「外見や肩書きよりも、心に届く言葉」を何より大切にしているからでしょう。
学歴や年齢よりも、“視点を変える力”を届けてくれる。
彼の文章や言葉には、そんな不思議な温かさと深さがあります。
これからも、ひすいこうたろうさんの発信を通して、
「ちょっとだけ心が軽くなる」「日常が少し楽しく見える」――
そんな小さな幸せの種を、私たちも見つけていけたらいいですね。
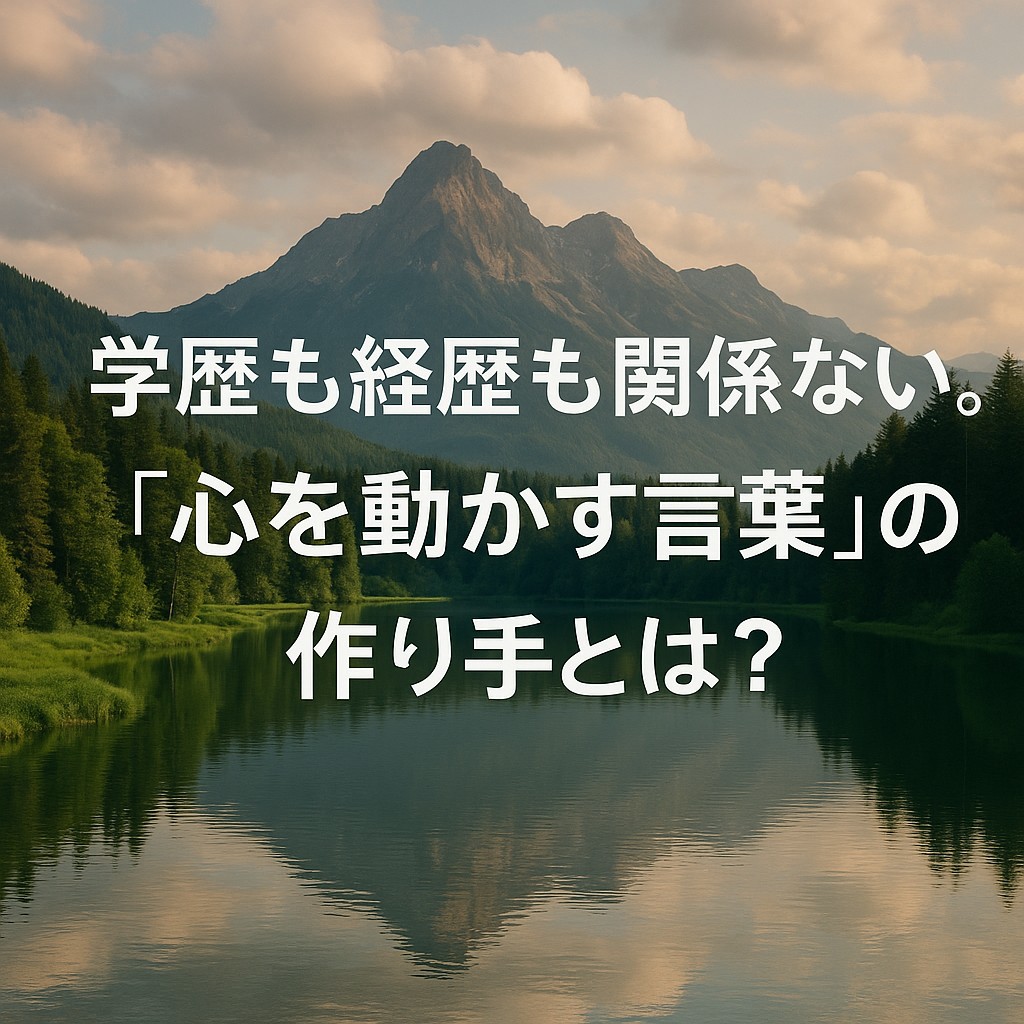
![3秒でハッピーになる 名言セラピー【電子書籍】[ ひすいこたろう ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1409/2000003491409.jpg?_ex=128x128)
![今日、地球人をやめる。 「日常」が面白い「物語」になる15の裏ワザ【電子書籍】[ OZworld ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/2093/2000017582093.jpg?_ex=128x128)
![3秒でもっとハッピーになる名言セラピー+ [ ひすい こたろう ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8875/88759446.jpg?_ex=128x128)


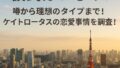

コメント